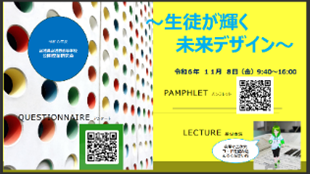学校行事
DXハイスクールの取組が「大學新聞2月10日号」で紹介されました
特色ある取り組み 「高校の力」 シリーズ25
美術科と普通科の強みを活かす STEAM教育 × DX による「デザイン思考」の醸成
新聞記事はコチラ ⇒ 宮城県宮城野高等学校_大學新聞第236号 .pdf
令和6年度 探究道場を実施しました
探究道場とは・・・
本校生徒がスタッフとなり、探究活動に興味を持つ中学生のみなさんが意見を出し合いながら課題解決に取り組むという活動です。京都市立堀川高等学校を拠点校として全国11校が連携し、探究テーマを決め、実験やオンラインミーティングを重ねて準備し実施しています。(コチラの紹介動画もどうぞ!)
今年は以下の2回実施しました。
① 7月27日(土) 『最強の耐震構造プロジェクト』
② 12月14日(土)『数値化プロジェクト』
先日実施した『数値化プロジェクト』では、身近にあるものを比較する際に「数値化」を用いてわかりやすく表現できないか、中学生の皆さん自身に題材と方法を考えてもらいました。
本校生徒の感想を掲載します
【どの班も数値化するにあたって何を言い換えるかが悩む様子が見られましたが、発泡スチロールの強度を比較した班では、様々な重さのおもりを一定の高さから落とし、できた凹みに粘土を敷き詰めその質量を量ることで数値化し比較することができました。今回のプロジェクトは高校生でも初めて知ることが沢山あり不安もありましたが、「高校生の支援によって探究を楽しめた」という中学生の感想ももらえたので、充実したいい経験になったと感じました。】
参加してくださった中学生のみなさん、保護者の方に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
探究道場は来年度も開催する予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。
公開授業研究会「生徒が輝く授業デザイン」を開催しました
11月8日(木)「生徒が輝く授業デザイン」とのテーマで公開授業研究会が行われました。今回は、他県からお招きした先生方と本校の教員が協働して授業を作り上げたものや、校内で切磋琢磨するなかで生まれた授業など、合計6時間分を公開しました。
◆「ICTを活用した学び」
「物理」…佐藤充恵先生(ドルトン東京学園、理科)、小林良英先生、菅原和哉先生が協働して授業公開。物体が弾むか弾まないかを「数値化」しながらカプセルを設計するユニークな授業実践でした。
◆「教科領域横断的な学び」
「歴史と文学」…佐藤哲郎先生(地歴科)、伊勢将聡先生(国語科)、川崎浩介先生(地歴科)が、教科の枠を超えて授業実践。『こころ』の「明治の精神」について国語的なアプローチと歴史的なアプローチから迫りました。
「言語文化 / 英語コミュニケーションⅠ」…鈴木幸恵先生、石垣将太先生、飯田宏先生、藤田彰子先生が協力して授業設計。「木曽の最期(平家物語)」を題材に日本とインドネシアの英雄像等について、Zoomでリアルタイムにインドネシアの高校生と中継して授業実践を行いました。
◆「探究的な学び」
「数学Ⅰ」…法貴孝哲先生(清真学園、数学科)、相澤正義先生が、数学を題材として、生徒を「しこう(思考・試行)」させるために生徒の学ぶ意欲を引き出す授業を実践しました。
「英語コミュニケーションⅡ」…山口和彦先生(山形東桜学館、英語科)、阿部彩先生が、英語による即興型ディベートの授業は迫力満点でした。
「体育」…片寄昌子先生、細川孝博先生が、iPadの動画撮影機能を活用し「movement off the ball」に着目したサッカーの指導で、生徒たちが考えながら体を動かす授業でした。
当日は高校、大学の先生方やNPO法人、大学生など30名を超える方々にご来校いただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。特に、公開授業後に3つの領域に分かれた研究協議会では「生徒が輝く授業デザイン」について質疑の時間を超えるほど、白熱した話し合いとなりました。
基調講演では、ベネッセ総合教育総合研究所主席研究員の山下真司氏をお迎えし、「これからの社会を生きる生徒たちに必要となる資質・能力を育む学びとは?」との演題でご講演をいただきました。個別最適な学び、自由進度学習など、これからの学びに向けて示唆に富んだ貴重な内容でした。
データサイエンスゼミ発進! ~ 東北大学データ駆動科学・AI教育研究センターとの高大連携事業開始~
10 月2 日(水)東北大学データ駆動科学・AI 教育研究センターから 栗林稔 教授、同大学院生2 名(鈴木碧月さん佐野光希さん)をお招きして、本校のデータサイエンスゼミがスタートしました。
ゼミの冒頭、栗林教授から「大学院生はみんなよりほんの少し知識があるけれど、データの見方や考え方はみんなの方が優れていることも出てくる。色々な見方をみんなで共有しながら楽しく進めていきましょう」とのお話がありました。
第1 回ゼミの目標は「いろいろなグラフでデータを表現してみよう」です。生徒は本校の 三品祐輔 教諭から与えられたデータを様々なグラフで表現していきます。友達と知恵を絞りパソコンとにらめっこした1 時間の試行錯誤の後、現れたグラフの曲線は、あの「世界的に有名なネズミのキャラクター」の形でした。
それぞれの画面にキャラクターが現れた瞬間、生徒達は達成感を爆発させ、友達とお互いの健闘を称え合うなど楽しんでいる様子がみられました。初参戦した二人の東北大学院生もすぐに馴染んでくれて、操作に悩んでいる生徒に積極的に声がけしてくれたり、それぞれに応じた的確なアドバイスを与えてくれたりと、とても楽しい学びの場を演出してくれました。
今後のゼミ活動では、コンペティション受賞作を題材にデータサイエンスの学びを深めていきます。12 月20 日に東北大学マルチメディア教育研究棟で予定されている「成果発表会」を目指して、東北大学院生と一緒にデータサイエンスの世界を楽しんでいきたいと思っています。
「生徒が輝く授業デザイン」公開授業研究会について(御案内)
「生徒が輝く授業デザイン」として下記のとおり公開授業を行います。
令和6年11月8日(金)9:40~16:00
会場:宮城野高等学校
本年度は基調講演として山下真司氏(ベネッセ教育総合研究所 教員イノベーションセンター主席研究員)をお招きしご講演をいただきます。また、全国の先進的な授業改善を共に学ぶために
佐藤充恵(ドルトン東京中等部・高等部 理科)
法貴孝哲(清真学園高等学校・中学校)
山口和彦(山形県立東桜学館中学校・高等学校)
の先生方をお招きし、授業づくりを考えます。
教育関係の方限定の参加となります。県内外の多数の参加者をお待ち申し上げております。
申込みURL https://forms.office.com/r/ZVWY3UnkrX
実施内容はこちらの授業公開.pdfを開いてください。